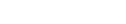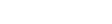多くの精神科医が目指さないのに、何故この道を選んだのか?との質問をいただきました。
『はじめまして』でも書きましたが、私には、多くの精神科医がどうして私と同じ道を選ばないのかが不思議で仕方がないんです。私にとっては、当たり前っていうか、精神科医になるならこれしかないじゃないか、という感じなんです。そう感じる自分が相当変わっているということになるのだと思います。
日本では、変わっていると考えざるを得ないし、圧倒的に少数派ですが、世界標準だと、そうでもないかもしれません。精神分析がアメリカでもすたれてきているという話を聞きますが、最近の映画でも、分析治療のセッションと思われるシーンがよく出てきます。日本でよりは、精神分析が社会に馴染んでいるのは間違いないと思います。
私は、医学部に入る時から精神科医になりたいと思っていました。そして精神科医とはこんなことをする職業なんじゃないかという漠然としたイメージのようなものを持っていました。精神分析関係の本を読んでいたわけではないのですが、なんとなく、とにかく患者と話をする、その中から何か変化を目指す、というようなイメージだったような気がします。大学を卒業し、実際に精神科の医局に入って、そのイメージが現実と大きくはなれていることに気づかされました。治療と言えば薬物療法、精神療法は個々人にまかされているという感じでした。薬物療法の専門家はいても、精神療法の専門家はいないんです。
ここまで書いて、この辺りのことをもう少し詳しく述べたくなりました。精神療法の専門家がいないというのは、私の主観としては正直なものなのですが、丁寧な言い方ではありません。その当時(今から38年前)、医局の中に、三つの研究グループがありました。生化学、神経生理、精神病理の三つです。前二つは、直接的には臨床と関係のない研究です。生化学の人たちは、ネズミを相手に向精神薬を使って色々な実験をしているようでした。神経生理の人たちは、脳波とか、眼球運動とかを機械を使って測定していました。いずれにしても、実験し、データを積み上げて論文を書くことを目指している人達なんだなと、それらの分野にほとんど興味のない私には、そんな風に見えていました。そして、ここのグループに属している人達は、精神療法がどうのこうのとかというようなことを、そもそもほとんど言いません。ところが、精神病理のグループに属している人達は、そうですね、精神病理学というのがどういう学問かということをまず説明しなければいけません。患者の病的な心理について理解しようという建前から、哲学用語などの難しい表現を用いて、ああでもないこうでもないと言葉を連ねる学問、という感じでしょうか。実験をするわけではなく、患者との臨床場面が直接の素材になるせいか、他のグループからは、精神療法についても一家言持っているとみなされる傾向があったんです。本人たちも、精神療法についての議論は自分たちの領域だとの気持ちを持っているようでした。
ところが研修医の私から先輩たちの臨床を間近でみていると、生化学や神経生理のグループの人たちのほうが、精神病理のグループの人たちより、ずっと治療が上手いんです。患者のよくなり方が違うんです。この違いは、薬物療法によるものではなく、精神療法などと特に意識していない人達のほうが、ずっと精神療法的だというところからのものだと感じました。この印象は、このころの私にとって、結構強烈なものでした。
今から思うと、ポイントは、頭でっかちかどうかだ、という気がします。精神病理グループの人達に、はっきりとその傾向があったと思います。
この頭でっかちさは、その頃何回か出席してみた、日本精神分析学会でも感じました。精神病理グループの頭でっかちさと、質は微妙に違うのですが、外国の文献を引用するのが大好きで、自分で感じたことよりも、すぐにそっちの話になるところは、全くそっくりでした。質が違うと感じるのは、引用する文献が、片方がドイツ語圏、片方が英米圏であるせいかもしれないと、今書いていて思いつきました。
当時読んだ本で最も印象に残っているのは、フリーダフロムライヒマンという女性精神分析家の、確か、Principles of Intensive Psychotherapyという題のものです。内容はもうほとんど記憶していないのですが、この人はちゃんと自分で精神療法を苦労してやって、その体験をわかりやすい言葉にしている、という感じがしました。この人のようなセラピストから教育分析を受けたい、と思っていました。
近藤先生に出会う前の記憶をたどってみて、あらためて、自分は師匠を求めていたんだな、と感じます。何故セラピストを目指したかと問われても、冒頭に述べたように、自分にとってはそれしかなかった、という感じです。