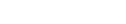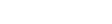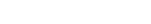依存支配型については、"優等生性"の亜型と位置付けている"奴隷性"について書こうと試みたところで止まっています。再度、"奴隷性"についての記述にチャレンジします。
依存する相手に忠誠を尽くす。相手の言うことを絶対的に正しいものとして逆らわない。自己主張しない。文句も言わない。愚痴もこぼさない。仮に、相手の要求が理不尽なものだとの感じがどこかで微かに生じても、自分はそれに従い耐えるしかないと決まっていて、理不尽さを指摘しようとか反抗するとかの発想自体が浮かばない。何も言われていなくても、自分への期待を察知しようとのアンテナを張り、その期待を実現するべく行動する。相手の期待、基準から外れていないかを常に自分でチェックする。相手の下に自分を位置づけ、従属的な態度を取り続ける。
この人のメインの防衛は奴隷性だなあと感じる方々の立ち居振る舞いは、控えめで大人しい。その雰囲気も加わって、この人は謙虚な方だなあとの第一印象を抱きます。実際に謙虚なところがあると言えないこともない。劣っていてダメな人間だから社会の下層に置かれ虐げられ傷つけられるのが当然だというような自己イメージが存在している。自己評価が低いと言ってもいい。しかし話を聴いているうちに、実は決して本当の意味で謙虚なわけではないことを知ることになります。場合によってはそのギャップの大きさのせいで、全体像を把握するのにめまいが生じるような感覚に襲われます。ギャップがそれほど大きくなくても、謙虚に見えてしまう側面とは別に傲慢さが必ず存在します。
ギャップが大きくてとりあえずは混乱してしまう例を挙げるなら、パッと思いつくのが、聖者とか神と呼ぶにふさわしい理想イメージを内心に抱いている場合です。自己犠牲的で他者を優先する自分を、人々に愛を与える聖者や神とみなしている。そして並の人間とは違う振る舞いができているとの優越感を満足させている。理想イメージが聖者とか神とかと呼べるほどではない場合でも、正しさへのこだわりは必ず存在します。ダメで劣等な人間かもしれないが、でも、正しい行いをしている、という気分があります。そして更に、その点では自分は優れているんだとの気分をひそかに抱いています。
謙虚さと内心での秘かな優越感とのギャップと同時に、このタイプの人には、もう一つのギャップが存在すると言いたくなる感じがあります。それはこの態度が実は自己中心的なものだという事実とのギャップです。自己主張的だったり、見るからに保身的だったりとかの、いわゆる自己中心的な態度とは正反対ともいえる態度だからです。聴いているこちらも、この態度の自己中心性に確信が持てるまでに時間がかかります。言葉を変えれば騙されやすい。本人が自分は実は自己中心的なんだと気づくのにも困難性が高いと言えると思います。呪いが覚めにくい。呪われていること自体に気づきにくい。
僕がこの態度の自己中心性に確信が持てるのは、忠誠を尽くす相手に安全を保証されるのが当然だという気持ちがあることに気づかされる時です。見返りを求めている。自己犠牲が無償のものではない。自己に対し手厳しく犠牲を強いるのと同じ強さで、相手に(母に、家族に、上司や所属する組織全体に、更には国に)安全の保証を要求している。
今、無謬性という言葉が浮かびました。自分も正しいが自分が依存する相手はもっと正しい。自分が所属する組織も正しい。自分の周囲には過ちは存在しない、正しさに包まれている。依存対象の振る舞いの変さをどこかで微かに感じても、取り合わない。ないことにしてしまう。自分が正しいことをしていさえすれば、自分が依存するからには自分よりも正しさの度合いが上であるに決まっている相手は、自分に安全を与えてくれるはずだ。何かの時に守ってくれるのは当然だし、何もなくても常に自分のことを心配し自分の安全に注意を向けてくれているはずだ。そういう幻想の世界に住んでいます。
この幻想の世界に安住していられるのは余程条件揃わないと難しいので、何かのきっかけで破綻を迎えます。一般的には幻想の破綻は内省に向かう大きなチャンスです。しかし、破綻してもなかなか内省に向かいにくいのが、またこのタイプの特徴です。大抵は、自分より正しい存在のはずの依存対象への批判、攻撃に向かいます。正しさをめぐる理想イメージ自体を客観視する方に向かいにくい。内省というのは自分自身を批判的に眺めることだとも言えると思います。正しいはずの自分の正しくないところは見たくない、という気分なのかもしれません。
僕の仮説を使うと、防衛はすべて潜在的孤独感を潜在したままにしておくためのものです。雑駁な言い方だと、実は傷ついているのに傷ついたと感じないようにするためのものだと言い換えることが可能です。だから、どのタイプの人にとっても、「自分は昔、母親との間で結構傷ついていたんだなあ」との実感は、防衛全体がある程度見えてくるまでは、なかなか生じない。この生じにくさが、このタイプの人では特に著しいと僕は感じています。このこともまた内省に向かいにくさに大いにつながっていると感じます。潜在する傷つき感が顕在に向かうことは自己肯定感の増加を促し、それはむやみに正しさにこだわらなくてもいいやという気分を生じさせます、余裕が生まれるとも言えるでしょう。
ここから先はspeculationです。「自分は昔、母親との間で結構傷ついていたんだなあ」という実感の生じにくさ。これは、傷つきを感じないようにする元々のやり方が、虐げられ傷つけられるのが当然だとすること(奴隷性)によって達成されているからに違いない、そう思うのです。仮想の世界で傷ついているから実際に傷ついていることには逆に気が付きにくくなる、可哀そうな自分というイメージが邪魔をして実際に可哀そうであることがピンと来なくなる、そんなことが起きているのではないでしょうか?
もう一つここで述べておきたいことを思いつきました。利用されることへの過敏さです。多くの人間関係は無償の友情や愛情で成り立っているわけではありりません。お互いの打算で成り立っている場合、ギブアンドテイクが釣り合って成立している場合、利害関係が一致している場合、いずれにしても、お互いにある程度は利用しあっているのが現実の人間関係だと思います。その現実を、大袈裟に被害的に、一方的に自分が利用されていると受け取る傾向があります。これも、自分の依存の在り方が利用と呼ぶのにまさにふさわしいものであること(最も手に入れたいものを獲得するために奴隷という役割を演じている)、そしてそのことに気づくのが難しいこと、と関係しているに違いありません。自分は目的があって尽くしているのに相手には無償で無尽なものを求めている。そしてそこに気づいていない。実は自分が相手を利用しようとしているんだという現実に気が付けば、今度は逆に、相手がいつもいつも自分を利用しようとしているわけではないことに気づくことになる、そういう関係にあると考えます。