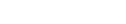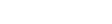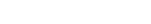子供を育てることとは?との質問に、子育てにおける女性(母親の)の圧倒的優位性についての僕の考えを述べてみます。間接的な答えにはなるかもしれません。
治療とは何か、あるいは治療の目指すものは何かについて、色々な言葉を使って述べてきましたが、また少し違った表現をしてみます。「ゆっくり風呂に入って少しづつ垢を落としていくようなものだ」。これも近藤先生の言葉です。自分の身を守る為に意識的に身に着けたものを脱ぎ、裸になって、くつろげる環境の中で、更に無意識的に身体に染み付いているものをもどんどん落とし、素の(originalな、genuineな、spontaneousな)自分に近づく、というイメージだと思います。
無意識的に染み付いているものがどこからやってきたか、社会からのもの、父親からのもの、母親からのものに分けると、母親からのものが、最も深く、強く、落ちにくい。臨床経験が増すにつれてそう感じる感じ方がはっきりしてきました。これを、子供に対する母親の影響力は、父親やその他の人間と比べようがないぐらい大きい、本当の意味で母離れして独立した人間になるのは非常に難しい、などと言い直すことも出来ると思います。父親の支配力、存在感が圧倒的に強い家庭でも、大した違いがないという印象を持っています。父親っていうのはなんと悲しい存在だと感じることがよくあります。子育てにおける父親の役割は基本的には母親(妻)をどう支えるかにあるのだと思います。
男性の側から、精子の立場に立って、受精の瞬間の様子を描写してみます。膣内に射精された何億個かの精子は、子宮頚部から子宮を通り、卵管にいる一個の卵子に向かって進んで行きます。相当数は途中で死滅し、卵子の周辺までやっとたどり着いた精子のうちのたった一つが卵子の中に取り込まれます。一つが取り込まれた後は卵子が作った膜に阻まれ他の精子はもう入り込めません。
ここが子育ての始まりです。卵子の側が精子を選んでいる様子、つまりは卵子の側が主導権を握っている様子がよく示されていると言えるのではないでしょうか?
ここから更に母親の胎内で10か月弱を過ごすことになるわけです。この間の胎児への母親の影響がいかなるものか、わかっていないことが多いと思います。ですが少なくても、父親のそれと比べようもないぐらい大きいものであることだけは明らかです。少しどぎつい言い方をします。この間父親が死んでも胎児の生命には直接関係ありません。母親の死はイコール自分の死です。
出産後しばらくの間も、この事情は、それほど変わらないのではないでしょうか。乳房の存在に象徴されているように、生命維持にとって母親の存在のみが必要だ、という事情です。その事情は、その後物理的には少しずつ変化し、母親のみが生命維持に必要なものを与える存在ではなくなっていくわけですが、子供にとっては、その物理的変化は客観的に見るほど大きくないのではないでしょうか。母の存在の大きさが続くのではないかという気がして仕方がありません。
クライエントを理解しようとする毎日を送っているわけですが、なんだかんだ言っても母親だ(の影響が大きい)よなあ、その染み付きは容易なことでは薄れないなあと感じることが、年を経るごとに増えているとはさっきも書きました。
それに加えて、勿論、基本的には個人による違いが最も大きいのですが、大まかに言うと、母離れの難しさは女性の方が強いようだ、という印象があります。娘が母親から精神的に独立することの難しさは、息子のそれより大きいと感じます。あるいは、娘の方が母離れしていなさを自覚しにくいと言った方が正確かもしれません。いずれにしても、このことは、女性のほうが伸びしろが大きい、成長出来る可能性をより多く残していることを意味していることになると思うのです。もともと自然や大地に親和性があり霊性に恵まれているのは女性の方だと思います。ですから、一人でも多くの女性たちが虐待の連鎖を断ち切る方向に進んで行くことを目指せば、ひょっとするとそれが一番、平和で豊かな社会が実現する近道かもしれないなどと夢想します。一代の母子関係でそれが実現できなくても、そういう意識を持った母親に育てられた子供には、道の向こうにたどり着く可能性が増しているに違いありません。
これは子育てに限ったことではありません。我々の仕事でも、子育てにおいてと同じように母親の圧倒的優位性が働いていると僕には感じられます。ケースカンファランスでの印象なのですが、セラピストが女性であるというだけで、我々男性セラピストを相手にするより、クライエントの側により大きな安心感が生じているように感じられてならないのです。残念なのは、多くの女性セラピストがその優位性を自覚しないままそこに甘んじているように見えることです。優位性を自覚し、更に、自分自身の母子関係の問題にもっと向き合って欲しいと願います。そうすれば素晴らしい女性セラピストが誕生するのではないかと思うのです。