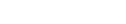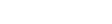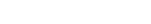完全主義についてはまだまだ書き足りないのですが、筆が進みません。僕の中での熟し方が足りないのかもしれません。少し置いておいて、先に、孤立型と依存支配型について書いてみようと思いつきました。その前に、これまでに出てきた仮説を整理し、まとめておきたいと思います。
潜在的孤独感というのが僕の仮説のキーワードです。子供の自発性と母親の自己中心性がぶつかることによって子供側に生じ、無意識に刻印されたものだと定義しています。
ぶつかった衝撃をそのまま衝撃として感じられない。ずれをずれとして認識できない。そこで、自発的な部分をダメなものだとする感覚が生じ、自己嫌悪の元となり、母親との一体感を得るため(見捨てられないため)の無意識的(後には意識的にも)な努力が始まります。環境に適応するための努力と言ってもいいでしょう。母という環境に適応するためのやり方が、若干の修正はあっても、ベースのところはほとんどそのまま、社会環境に適応するためのやり方になります。僕は、自発性と強迫性とを対比的に使うのが好きですが、この努力は強迫性を帯びざるを得ないということになります。
次に、このようにして始まった、環境に適応しよう(生き延びよう、安全を得よう)との努力を、価値づける心理が生じます。そして、外からの色々な刺激とあいまって、理想の自己イメージが形成されます。これらのプロセスのほとんどは無意識のうちにおこなわれます。
努力が向かう先、理想の自己イメージ、に対する態度の違いを、(狭義の)ナルシシズムと完全主義とにわけました。自己イメージに割と簡単に同一化出来てしまうグループと、なかなか同一化出来ずにさらに努力を続けようとするグループです。
もう一つの提案があります。心を三つの層にわける見方をここで導入したいのです。これも近藤先生からのものです。盗用して僕なりに使わせていただくことにします。
第三層というのを、我より深いところにあるもの、我と拮抗する傾向があるものとして捉えています。誰にでもあるけれども、殆どの人が自覚していない層です。我々を超えたものに生かされていると感じる事が、その層の体験を代表します。祈り、感謝、安心、歓喜の層であり、創造性の源でもあります。霊性とか宗教意識とかの表現がピンとくる方がいるかもしれません。人間の深い自発性と連帯している層だとも言えるでしょう。
潜在的孤独感というのが僕の仮説のキーワードです。子供の自発性と母親の自己中心性がぶつかることによって子供側に生じ、無意識に刻印されたものだと定義しています。
ぶつかった衝撃をそのまま衝撃として感じられない。ずれをずれとして認識できない。そこで、自発的な部分をダメなものだとする感覚が生じ、自己嫌悪の元となり、母親との一体感を得るため(見捨てられないため)の無意識的(後には意識的にも)な努力が始まります。環境に適応するための努力と言ってもいいでしょう。母という環境に適応するためのやり方が、若干の修正はあっても、ベースのところはほとんどそのまま、社会環境に適応するためのやり方になります。僕は、自発性と強迫性とを対比的に使うのが好きですが、この努力は強迫性を帯びざるを得ないということになります。
次に、このようにして始まった、環境に適応しよう(生き延びよう、安全を得よう)との努力を、価値づける心理が生じます。そして、外からの色々な刺激とあいまって、理想の自己イメージが形成されます。これらのプロセスのほとんどは無意識のうちにおこなわれます。
努力が向かう先、理想の自己イメージ、に対する態度の違いを、(狭義の)ナルシシズムと完全主義とにわけました。自己イメージに割と簡単に同一化出来てしまうグループと、なかなか同一化出来ずにさらに努力を続けようとするグループです。
次に、努力そのものの質の違いを、大きく、孤立型と依存支配型にわけようと考えています。そしてこのような努力の総体を"我"と呼んだらどうだろうと提案します。孤立型と依存支配型という見方を横軸に、完全主義とナルシシズムという見方を縦軸にして、その人の"我"の全体を理解しようというわけです。
もう一つの提案があります。心を三つの層にわける見方をここで導入したいのです。これも近藤先生からのものです。盗用して僕なりに使わせていただくことにします。
繰り返しますが、我とは、潜在的孤独感を潜在的にしておくための意識的無意識的な努力の総体です。その努力のうち、知的な面、思考、想像、イメージなどを第一層、感情や本能,身体性に関わる部分を第二層と呼ぶ、ということにしたいのです。
第三層というのを、我より深いところにあるもの、我と拮抗する傾向があるものとして捉えています。誰にでもあるけれども、殆どの人が自覚していない層です。我々を超えたものに生かされていると感じる事が、その層の体験を代表します。祈り、感謝、安心、歓喜の層であり、創造性の源でもあります。霊性とか宗教意識とかの表現がピンとくる方がいるかもしれません。人間の深い自発性と連帯している層だとも言えるでしょう。
この見方を導入して、治療の流れを描写してみます。まず、第二層に注目します。色々な感情を少しづつ掘っていきはっきりさせる。そして受け入れられるようになる。別に言うと、不安を友達として、怒りや嫉妬に向き合い、次第に潜在的孤独感に近づいていく。その方向への動きと軌を一にして、第一層を含めた我がそれとして全体的に見えてくる。それらの進行とともに、母とのずれによって伸びることが抑えられていた自発性が、息を吹き返し、育ってくる。
三つの層に対応させて、我が全体として見えてくるプロセスを第一プロセス。浅い感情から深い感情まで徐々に受け入れていくプロセスを第二プロセス。自発性が育ってくるプロセスを第三プロセスと呼ぶ、というアイディアが浮かびました。
治療というのは、この三つのプロセスが有機的に関連しあいながら進行していくものだ、と言えそうです。第二プロセスが進行し、ついに、過去の母親とのずれが傷として刻印されていることを感じるようになった時、つまり、潜在的孤独感が潜在的でなくなった時、その地点では、我が全体として見えるようになっていることにもなります。それまで少しづつ育ってきていた自発性が、その地点を境にして、場合によってはひとっ跳びに、その深さを増し、ついに第三層からのものとして感じられるに至る。その体験を治療の最終目標だと位置づける。これが僕の仮説の概略です。