『敏感さについて その一』を書いている途中から、その二を書くつもりでした。まだまだ書き足りないことがあるような気がしていたのです。具体的にもいくつかのアイディアが浮かんでいました。今実際に『その二』を書こうとパソコンに向かってみると、その時に予定していたものとはかなり違った内容になりそうで、そのことをまず最初に報告したくなりました。
あの文を書いた後、何人もの人との間で、書いた内容の重要性が証明されたように感じる場面が重なりました。その感じが新鮮で面白く、『その一』を書いている時に浮かんでいたことがらはどうでもよくなってきたのです。
その感じを少し詳しく述べてみます。
『その一』の最後に、敏感さに目を向けることが不安や緊張の耐えやすさにつながることを願う、と書きました。そう書いた勢いで、『その一』で触れた二人以外にも、不安や緊張に関連する話題が出た時、僕の方からより積極的に、素質としての敏感さを指摘する頻度が増したのです。と同時に、敏感であることを価値づける僕の価値観をよりハッキリと打ち出すにようにもなりました。それに対して様々なレスポンスがあったわけですが、そんなやり取りを通じて、僕の側の確信の度が深まってきたというような感覚を味わったのです。確信というのは、素質としての敏感さと不安との本質的なつながりについて、不安に耐えることの治療的な意味について、敏感さが人間にとって最も重要な素質だということについて、です。平たく言うと、「ああ自分が言ってきたことは間違いじゃなかったなあ、そしてかなり本質的に重要なことなんだなあ」というのが近い感じです。
こう書くと、それでは今まではそんなに強く確信しないまま、例えば、「不安と友達になれ」と言っていたのか、という突込みが浮かびます。この突込みには反論できません。そういうことになりますね、としか言いようがない。言っている内容が仮に正しくても、それを言っている人がどれだけ確信を持って言っているか、それが重要だ。このホームページの院長挨拶で、似たようなことを僕が言っています。自分で言っていることを自分で実行できていないわけですが、有言実行に少しは近づいた、とも言えそうです。僕にとっては、この、敏感さに関する確信が深まってきたという感覚は嬉しいものです。
そして更に、上記の確信が深まってきたこととつながって、傷つくことがいいことだ、というフレーズが浮かぶようになりました。このフレーズは事態を正確に言い表したものではないという感覚も同時に生じます。正確に言うなら、傷ついていると感じることがいいことだ、になるのだろうと思います。でも、傷つくことはいいことだと言ってしまいたい。
敏感さと傷つきやすさ。『その一』で触覚についての例を出しましたが、敏感であればあるほど傷つきやすいとは言えそうです。そして人間恐らく例外なく、傷つきそうになるとなんとかそれを避けようとする。傷つきを避けるためなら手段を択ばない、なんでもするとさえ言える。とすると、敏感であればあるほど避ける方にネルギーが向かいやすい。言い方を変えれば、敏感な人ほど自分が傷ついていることに向き合いにくくなる、つまりは何とも皮肉なことに最も身近なことを感じにくくなる(鈍感になる)。どんなに避けようとしても傷つくことから逃れられないのが現実だと言えるとすれば、敏感な人ほど現実的になりにくい、幻想の世界に入り込みやすい。
その幻想に打撃を与えるためには、正確さを選ぶより、傷つくことがいいことだと言ってしまったほうがいい。そんな感じです。
傷つきを傷つきとしてごまかさずに感じ、引き受けること。それはイコール依存の自覚でもあります。また同時に、孤独の体験でもある、という感じがします。
『その一』を書いた後のやり取りの中で、敏感さと過敏さの違いは何か、という話題も何人かの人と話し合うことになりました。
何か目立たないものを感じる、多くの人が感じられないものを感じる、それが敏感さだと思います。そのことは絶対的にいいことだ、というのが僕の主張です。そして、何かに敏感だというのは素質に負うところが大きい、ほぼDNAに規定されている、と僕は考えます。一方、過敏さとば、素質とは直接的に関係がない、敏感さとは次元の違う概念だ、と捉えるのがいいと考えます。そして過敏になるためには、感じる事実を否定しようとする心理傾向がその人の中にあることが必要条件になると思います。感じることが葛藤状況を引き起こす。感じることが不安や恐怖を伴うことになる。そして最初の感じを消せず、否定しようとする心理の側からそこに意識的無意識的に注意が向いてしまう時、過敏と呼ばれる状態になる。主観的には、強く、刺激的、不安定、苦痛であり、はたから見ると大袈裟。
津川クリニックには歩いて通っていました。学生の多い土地柄もあるのでしょう、途中の道で吐しゃ物に遭遇することがよくありました。それを目撃するとまず何かの感じが生まれます。嫌悪感、が近いでしょうか。ここで注目するべきは同時瞬間的に吐しゃ物から目をそらそうとする動きが生じていたという僕の心理的事実だと思うのです。嫌だ、汚い、と感じることを否定しようとしている気がするのです。感じることをめぐっての葛藤状況が引き起されていると言えそうな気がするのです。この時、目をそむけようとする心理の側に自分が立つと、後から吐しゃ物のシーンが繰り返し思い出される。心理的葛藤が自分にあることを正直に自覚すると(大雑把に言えば、ああ嫌だなあとちゃんと感じれば)後に残らない。ささやかですが、僕の実体験です。過敏さと、そこからの脱出を示唆する一例だと言えないでしょうか。

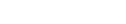
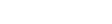


コメントする