「治療者と患者が出合い、治療契約を結び、禁欲規則を守り、ともに治療を行うところまではフロイト派と全く同じだが、そこから先に大きな違いがある。さまざまな幼児期体験の中で、自己の不安な存在を防衛するために無意識に一定の神経症的態度が作られ、この誤った自己像を価値づけ、真実の自己が疎外されているのが神経症の状態だ。応える能力(ability to respond)、応えること(respond)は、患者の人間としての存在の底に潜み、その底から呼びかけている真の自己の声(calling)に応答することだ。これが治療者の責任(responsibility)の深い意味である。この呼びかけと応答が、治療者と患者両者の絶えざる責任関係として深められ発展するのが治療関係である。それだけに治療者にとっての治療の場は、鏡のように客観的に観察する場ではない。むしろ、"responding to call,call and response"という関係であって、治療者が第三の耳を澄ませて聴くならば、その患者の願いが聴こえる。患者自身にunconsciousなものを我々は聴く。それを我々はsensitiveに聴き、respondする。我々は自分のイメージを押し付けるのではない。患者が本当に願うものにrespondする。そこから自然に技法というものが出てくる。」
近藤先生が、日本精神分析学会の第6回大会(1961年)のシンポジウムで語られた内容なのだそうです。この学会の重鎮であり続けた故小此木圭吾先生が、近藤先生がなくなられた年、1999年の4月の学会誌(精神分析研究43巻2号)に、近藤先生を偲ぶ文を寄稿されています。その中で、1961年の近藤先生の発言を以上のように回想し、この治療感覚は現在の私(小此木先生)の治療感覚とも大いに共通のものがあるが、あの当時も大きな感動をおぼえた、と述べておられます。
分析学会の顔のような存在だった小此木先生が共感するという、分析学会のシンポジウムでの近藤先生の発言。治療とはこういうものだ、治療者患者関係とはこういうものだ、との近藤先生の考え。
僕としては、素晴らしい、全くその通りだ、自分はこれを目指しているんだ、と言いたくなります。
そして、精神分析学会の場で精神分析という名称の下に語られているけど、その呼び方はこの内容にそぐわない、という感覚が生じるのを止められません。
分析という言葉のどこに違和感を感じるのか?と自分に問いかけてみます。上記の近藤先生の発言の一部を借りて、分析という言葉は"客観的に観察する場"にふさわしい、と言いたくなるのを発見します。分析という言葉は、自分の外側にあるものを客観的に対象として観察する、暗黙のうちにそういうことが前提とされている、という気がして仕方がないのです。
responding to call,call and responseと言う時、相手のcallをこうだと感じるのは自分の主観で、その主観を元にしてrespondする。結局のところは、相手のcallをいかに正確に、ずれずに感じ取ることが出来るか、に行き着くと思うのです。第3の耳の感度を上げるということに尽きると思うのです。患者自身にはunconsciousなもの、つまり患者自身は主観的に感じていないことをこちらがこちらの主観で聴く。そしてrespondする。
第3の耳の感度を上げるというのを、直観力を磨くと言ってもいい。色々な表現はありそうだけど、いずれにしても、主観に徹するしかない、ということだとしか僕には考えられないのです。
そして、主観に徹する覚悟が決まり、主観を磨いて行く時、対象についての理解が次第に深まり、正確なものになっていく。このことは疑いようがない。とすると、主観が磨かれることイコール客観性を増すことだと言えるのではないか。先に主観がある。主観抜きの客観はあり得ない。
最初から客観的であろうとする態度に分析という呼び方はピッタリするが、我々の目指す治療にはふさわしくない。
このあたりが僕の違和感の正体だと考えます。ですが、それではどういう名称がピッタリか、見つけられないで現在に至っているわけです。
最近あるクライエントに、以上のような内容を話す機会がありました。分析されることへの抵抗感を表明したことへのレスポンスでした。その話し合いのあと、それまでなかなか内面を開かなかったその人が、明らかにその態度を変え、治療に積極的に取り組むようになったのです。強く印象に残る出来事でした。

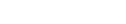
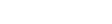


コメントする