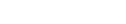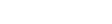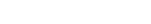最初の高血圧発作の時、「鉄槌を下された」感じがした、と書きました。ガーンと後頭部を殴られた感じ。僕には、何か目に見えないものが自分を叱っている、傲慢さに気が付けと言っている、そんな風に感じられたわけです。そして、その後現在まで、何をどのように叱られたのかを知りたい、という気持ちがくすぶり続けています。そのためには、高血圧発作の後新たに生じた不安が大きな手がかりになるような気がします。その不安のメッセージを正確に受け取ることが、鉄槌に意味を知ることにつながる。そう思えて仕方がありません。
今現在、下腹部に感じられる不安感がすっかりなくなったわけではありません。しかしそれでも、主に呼吸法をしている時に、そこに向き合う、そこの部分と対話する、そこからのメッセージに耳をすますつもりになる。そういうことを繰り返しているうちに、高血圧発作直後のそこの感じが少しづつ確実に和らいできていると感じます。その変化と並行して、不安からのメッセージをどのように受け取るか、言葉として浮かんではいてもなんとなくぼんやりしていたものが、次第に確信と呼べるものに近づいてきました。
コロンブスの卵という言葉があります。わかってみればとてもシンプルで当たり前に思えることなのにわかるまでには苦労する(工夫がいる)、と解することが許されるなら、僕にとっては、以下がまさにコロンブスの卵のような発見に思えるのです。
自分の力で何とか生き延びようと必死になることが自己中心性の元だ。
そして、これが不安からの僕自身へのメッセージだ、という気がして仕方がないのです。
自分の中に常に生き延びようとする力が働いている、自分の力で生き延びようとしている。これがハッキリしたのは、不整脈の出現によってです。不整脈のせいで心停止が起きるかもしれない、もしそうなったら何とか手を打つべく常に心拍を観察し見張っていなきゃいけない。そういう心理でいる自分に気が付いた。そして、これってナンセンスだよな、という気持ちと同時に、俺は生き延びたいんだなあ、そのためにはなんだってやろうと思ってるんだなあ、というような感慨が生じたのです。
そう気づいてみると、癌ノイローゼの時にも同じ心理が働いていたことに思い至りました。ちょっとした体の不調を癌ではないかと想像する心理が症状を引き起こしている。最悪の事態を想像している。最悪の事態を想像する心理というのは、日常の臨床で本当に良く遭遇する心理です。その想像が悪循環を呼び不安を拡大させる。パニック発作ではその悪循環の様子が最も見えやすいが、色々な症状がこの心理と関係して出てくるのは間違いない。
そしてこの想像が出てくる出どころは、実は、何とかして生き延びたい、そのための絶対の安全保障が欲しい、という必死な思いにある。危険を間違いなく回避するためにはあらかじめ最悪の事態を想定しておかなければならない。保険を掛ける心理だと言ってもいい。その心理が暗示として働いて症状が出現、症状が出ると検査を受けずにはいられなくなる。検査結果が出てとりあえずの安全が保障されたとたんに症状がなくなる。しばらくすると、無意識は更なる安全保障を求めて次の症状を産出する。そのように考えると、なんとまあ俺は自分のことしか考えていない自分勝手な奴だという感慨とともに、あの年の9月から12月の自分の行動の説明がつくように思えるのです。
不整脈の時の身構える感じ、この感じはまた、高血圧発作の時の、不安を隠そうとする態度に通じます。身体の感覚としてそっくりです。ゆだねられずに自分で何とかしようとする。そしてそれが悪循環を呼び症状が悪化する。そこも似ています。
不安を隠そうとするというのは、近藤先生との間ではっきりさせてきた僕の"こび"の根元にある心理です。自分の不安を押し殺し、呑み込んで、母からそれを隠すことが母に見捨てられない道だ。それを別に言えば、母との間で生き延びるためにはそうするしかなかった、ということになるのではないでしょうか。
自分の力で何とか生き延びようとする。そしてそのことが、自分の神経症的人格構造、すなわち我、を作り出す大元のエネルギーだ。自力で生き延びようとすることイコール自己中心性だ。そう考えると、鉄槌の意味もわかる気がしてきます。あの頃の自分は、開業して10数年、医局では初めての自費診療のクリニック。そんなやり方で経営が成り立つのかと多くの先輩や同僚から心配されたけど、今は一日8枠がすっかり埋まり、キャンセルが出ると待っている人がいる。大したもんだって思ってもらえているんじゃないか。そんな風に誇る気持ちがありました。1日8人とのセッションは、本当は相当きつく感じているのに、その感じを軽視していた。軽視して無理を重ねてしまううところに、自力性が大いに関与していた。そういう自分を自分で誇りに思う気持ち、まさに傲慢と呼ぶのがふさわしい。そこに対しての鉄槌だったのではないか。
最後に、ここが一番大事かもしれないことを書こうと思います。
自分の力で生き延びようとしていることへの実感が増せば増すほど、実際に自分が今生きているのはそのこととは無関係だということがハッキリしてきます。自分の、その生き延びようとする努力があるから生きているわけではない。その努力はむしろ自分の生命を害する方に働いている。今自分が生きているのは何か自分を超えたものに生かされているとしか考えようがない。