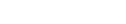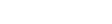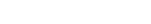『精神分析は宗教か その二』まで書いてみて、沸き起こってきた感じがあります。
精神科医だったら精神療法を目指すのが自然であたりまえのことだと感じるが、ほとんどの精神科医がそっちに進もうとしない。それが不思議でならない。このブログのどこかに書きました。精神療法を目指せば宗教とのつながりに直面することになるのが当たり前だと感じるが、ほとんどのセラピストがそこに言及しない。それが不思議でならない。沸き起こったものとは、この二つの、僕の中ではとても似ている感覚です。
僕にとっては当たり前のことが、多くの人にはそうでないらしい。昔から、いろいろな場面でそう感じて生きてきた気がします。そのほとんどの場面で、感じていることを表現せずにきてしまった。ここでは、精神療法を目指せば宗教とのつながりに直面せざるを得なくなるのが当たり前だし、もっと単純に、精神分析は宗教そのものだと言ったって良い、という感じをなんとか表現するべく奮闘してみます。
我々を超えたものがこの世に存在するというところまでは、多分誰にも否定できないのではないかと想像します。そこはまだ信仰の問題ではない。こう書いて、いやひょっとするとそうでもないかもしれない、との疑いが出てきました。我々を超えたもの、人知の及ばざるもの、僕にとってはそういうものの存在は疑いようのない事実ですが、僕にとっての当り前は多くの人にとっての当り前ではない。誰にも否定できないという僕の想像も当てにならない。我々を超えたものなど存在しない、現時点では人間の力が及ぼないように見えるものでも、人間の知性の進歩によって人間がなんとかできるようになる。そんな風に主張する人がいそうな気がしてきました。とすると、ここからもうすでに信仰の問題なのかもしれません。
我々を超えたものがこの世に存在するということ。それを神と呼ぶか、造物主と呼ぶか、あるいは自然の中にそれを見るか、名称はどうでもいい。心臓を自分が動かしているわけではないという事実を知的に考えてみただけでも、そういうものの存在は疑いようがないと僕には思える。そしてそこに、何か不思議さのようなものを感じるというか、感動が生じるというか、知的なものだけではない動きが出て来た時、それを宗教的体験の始まりと呼びたい。
我々超えて、普遍的で、永遠性のあるもの。そういうものを感じ、感動を体験する機会が増えてくる。そして更に、自分自身がそういうものに生かされているんだという感覚がはっきりしてくる。自分の根底にそういうものが息づいている、生き生きと動いていることを発見し、感じ、この世のすべての人とのつながりを、人だけではなくすべての生きとし生けるものと、更には岩とか土とか鉱産物とかの無生物とも、つながっているという実感に至る。そのような体験のプロセスを、信心が篤くなるとか、宗教的境地の深まりとかと捉えたい。
一方で、精神分析も体験です。まず、自分が感じていることを言葉にして出す。その行為を続け、それに対するセラピストの応答を聴く。聴くだけではなくセラピストの態度からいろいろなものを感じる。この人は自分のことをわかってくれていそうだという感覚をベースにして、自分について何かを発見する、気づく。それらが繰り返されるとともに、つまりは自己観察力が増すと伴に、自分に変化が生じていることを体験する。
僕がまず強調したいのは、両方とも、体験することにしか意味がない。体験がすべてだ、ということです。これも、当たり前のことだとは思うのですが、一応、書いておいたほうがいいという気がしました。
次に言いたいことは、それぞれ別のものであるかのように描写した体験のプロセスは、実は、重なり合っている。全く同じだと言ってしまうと言い過ぎの感じがあるが、とにかく別物だとは思えない、ということです。あるいは、次のように言うのがいいかもしれない。精神分析的な方法以外でも、先ほど宗教的な体験として描写したプロセスを歩むことは出来るかもしれないし、多くの先人達が実践し、実現して来たに違いない。しかし、精神分析がある程度市民権を得ている今の時代では、精神分析的な方法を使って体験を積み重ねることが、宗教的な体験を得るのに最も身近でかつピッタリしたもののような気がする。
精神分析的な方法を使うとは、自己観察力を増やしていく道を進むのに精神分析的な人間理解を地図として用いる、という意味合いです。具体的に言えば、自分自身が精神分析を受けるということ、そして被分析者を卒業したら、自己分析を続ける、ということです。
何故精神分析的な方法を用いるのが身近でかつピッタリしているのか、その件は少し置いておいて、先に進みます。
ここで、精神分析の創始者と言われているフロイドが宗教を批判したことについて、何かを言わなければならないという気がしてきました。フロイドは、宗教は幻想であり神経症である、と言いました。日々のセッションの中で、僕は、「それはあなたの個人宗教だ」とクライエントに言いたくなる時があります。育つ過程でその人に染み付いた主観的価値を客観的に見ることがむつかしく、そこへのしがみ付き方が、そう呼ぶのにピッタリする感じがする場合があるのです。フロイトの批判している宗教(的観念)と僕が個人宗教だと呼びたくなるもの。同じものを見ているのではないか、という気がします。その理解が間違いでないなら、フロイドの批判する宗教と僕の言う宗教性は全く違うものだ、ということになります。
フロイトは更に、そこ(宗教的観念の幻想性)から抜け出すためにこそ精神分析的な思考が必要だ、そこで最も重要なのは自己観察的な態度だ、とも言っていると記憶しています。ここは、言葉通りだとするなら、ほぼ賛成です。しかし、フロイドのいう精神分析的思考は、知性的なものに重きを置き過ぎているのではないか、と感じます。
自己観察について、フロイドが多分、あまり注目していない点に目を向けたいのです。分析治療中、分析者が被分析者に被分析者の神経症的傾向を示したとします。ここでは、その指摘が正しいものである、とします。被分析者が自分のそこを見て、「なるほどなあ」と感じる。そして、その神経症的傾向が徐々に減ってくる。被分析者の自己観察力が増し被分析者のパーソナリティーに変化が生じた、ということになるわけです。こういうことが生じることを狙って日々の臨床に臨んでいると言ってもいいのですが、この現象に接すると、僕は、なんとも不思議な感じに襲われるのです。
自分の神経症的傾向を見るように促され、そこを見て、「なるほどなあ」と感じる。書くと、簡単にそうなりそうに聞こえるかもしれませんが、これが実際にはなかなかそうはならない。見て、「ああ先生の言うとおりだ」と仮に言ったとしても、「ああなるほどなあ」っていう感じからは遠い。芯から納得しているわけではない。痛感していない。腹の中でいろいろな反論が浮かんでいるのかもしれない。薄々当たっていそうだなという感じがある場合でも、ピンと来たという感じからは遠い。これが普通です。このことは多分、日常生活で友人や家族から何かを指摘されたことを思い出してもらえれば思い当たるのではないでしょうか?余程の条件が揃わないと、その指摘を「ああなるほどなあ」と素直に納得し、肚に納まる感覚にはなりにくい。
僕が不思議な感じに襲われるのは、普通には滅多に揃わない条件が揃ったとしか考えられない現象が起きているからであり、その条件を整えるのに自分(そしてクライエントも)が関与した部分は非常に少ないと感じるからではないかと考えます。自分(そしてクライエント)以外の何かの力が働いたことで条件が整い、クライエントが「なるほどなあ」と納得するに至った。そう考えざるを得ない。考えるというより、そういう力が働いているのを感じざるを得ない。
このことは、気が付いたその神経症的傾向が減少するところ、パーソナリティーに変化が生じるところ、にも当てはまります。僕はよくクライエントに「気が付いたのはいいけどそこを自分の力で変えようとするな」と言います。気が付くと、なんとか自分の努力でそこを変えよう克服しようとするのは人情のような気もします。でも大抵ははうまくいかない。逆に、空回り、悪循環に陥る場合が少なくない。
気が付き方が増す方向、ただ実感が増す方向、認識が深まる方向を目指すのがベストだ。そうしていると何故だか不思議に変化が生じる。これが僕の実感です。変化を生じさせる力、自然治癒力、の偉大さを感じさせられる。我々の治療は自然治癒力に大きく依存している、と言ってもいい。フロイドだって自然治癒力を否定しているはずはないし、我々がそこに依存せざるをないことは認めていると思います。でも、依存する度合いに(実は大きく依存しているんだということを認識する度合いに)、自然治癒力の大きさの見積もりに、圧倒的な違いがあるのではないかという気がするのです。
そして僕は、分析治療の中で、この自然治癒力の働きを感じ、その偉大さに感動する体験を宗教体験の始まりと呼びたい。フロイトが批判したような宗教を偽物の宗教と呼ぶとするなら、本物の宗教性が育つ契機がここにある、と言いたい。