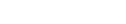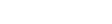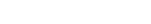『孤独とつながり』について教えてくださいとの質問がありました。
この質問者のメールから、最近友人と会い、いつものような会話をしていたつもりが、自分にとっては重要なことについての自分との感じ方の違いがはっきりし、今までその友人とつながっていると思っていたことに疑問を感じた、といった体験があった様子が読み取れます。それがきっかけになって出てきた質問のように受け取れました。
また近藤先生の言葉です。「人間関係っていうのは誤解でなりたってんるんだよ。」分析を受け始めたころに聞いた気がするので、もう30年以上前です。その後、その言葉が繰り返されることはなかったのですが、強烈に印象に残っています。
僕の今までの友人関係を振り返ってみると、大雑把に言えば、段々段々誰ともつながっていないことがはっきりしてきた、という感じです。つながっているという誤解が醒めてきた、孤独を実感する度合いが増してきた、ということでもあります
孤独を、恐怖感、自己嫌悪、自責、さらにはセンチメンタリズム、それらの感情とは別に感じることが大事なのではないか、という気がします。孤独感を他の感情を混じえずに感じる。あるいは、混じっていることがわかりながら感じる。そのように感じる孤独だと、感じれば感じるほど、結果として、人に優しくならざるを得なくなる気がします。
孤独を自覚せず、あるいは上記の感情と分離しないまま、人とのつながりをどうしても求めてしまう。それが人間の姿だと思います。そこには自分については勿論のこと、相手の正しい理解もありません。さっきの近藤先生の言葉を、このように解することが出来ると思います。
孤独を感じないでいられるように他人との一体感を求めざるを得ないのが人間というものだが、その一体感は幻想だ、と言おうとしています。一見人間関係をほとんど持たない引きこもりの人も、孤独感を、恐怖や自己嫌悪や自責、センチメンタリズムと別に体験してはいませんし、むしろ、孤立していながら孤独感を全くと言っていいほど感じていない場合も珍しくありません。
質問者に対しては、この質問のきっかけになった体験に質問者の成長が出ている、と言いたいと思います。友人とのずれを感じて動揺するでしょうが、その動揺を、自分がおかしいと結論付けたり、相手に無理に合わせることで解決しようとしたりせず、動揺に(孤独にと言ってもいいかもしれません)耐えるつもりになって欲しいと願います。