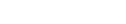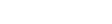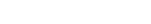沈黙について書いて欲しいとのリクエストがありました。
沈黙というと、セッション中のクライエントの沈黙をまず連想します。
ちょうどいい機会なので、診察室での、僕とクライエントの位置について書くところから始めてみます。
初回は、必ず対面です。治療契約を結んで、時間(一回50分です)が余った場合、その日から、ベッドに横になって話すようにお勧めしています。そうでない場合でも、二回目か三回目には試して貰っています。仰向けに天井を向いて横になり、僕は、頭の斜め後ろにほぼ同じ方向を向いて座ります。僕の顔が見えません。
この位置取りの意味についての近藤先生の考えは次のようなものでした。「一つは、セラピストとクライエントが同じ方向を向いているということ。共通の目標に向かって共に歩んでいることを表していることになると思う。もう一つは、沈黙している時にクライエントが孤独を体験出来るということだ。」
この位置取りを試してみること自体に抵抗感を感じる方もいますし、試してみて、やっぱり対面の方が話しやすいという方もいます。その場合はもちろん、対面でのセッションが続くことになります。
対面の方が3割で、ベッドが7割です。
セッション中のクライエントの沈黙は、ベットの場合が多いという印象があります。顔が見えない方が黙っていやすいのは当たり前かもしれません。
一人、僕にとっては忘れられないクライエントがいます。5年ぐらい定期的に通院していた30代の男性です。初めから、連想に詰まりがちで、沈黙の時間の多い人ではありましたが、途中から、50分、最初から最後まで一言も話さない回が出てくるようになりました。50分過ぎてブザーがなると、黙ったまま立ち上がり、身振りで別れの挨拶をして帰ります、そして受付で、次の予約をしていきます。そういうセッションが2,30回はあったと記憶しています。受診理由の一つは職場に行けないというものでしたが、沈黙のセッションが続く頃、勤務は続けられていました。でも結局は、治療が中断することになりました。
さて、近藤先生の言う、沈黙の治療的意味ですが、僕自身の被分析体験から言うと、そんなにピンときません。その理由の一つは、どこかにも書きましたが、僕が連想に詰まって黙っていると、先生の方が話し出すので、孤独を感じている暇がなかった気がするからです。
むしろ先生の孤独を感じたと言うと、ピンとくる感じがあります。孤独を引き受けている、その上でゆったりとそこに存在している、その雰囲気が伝わってくる感じがあった、と言っても近いです。僕が話している時はとにかくよく聴いてくれるし、不自然な口の挟み方をしません。黙っているならいつまででも黙っていそうで、そもそもが沈黙的態度だった、とも言えそうです。
さっき例にあげたクライエントの沈黙に対して、「話せないのにも理由があると思うからそこも含めて受容しているつもりでいる。話せるようになるのを待っている。」と伝え、後のほとんどの時間、僕も黙っていました。僕にはそうするしかありませんでした。その時間、僕が何を感じていたのかと、今、思い出そうとした時、クライエントの孤独と、孤独を引き受けられなさを感じていた、というセンテンスが浮かびました。当時、そんな風に言葉になっていたわけではありません。そして、僕のその時の沈黙が、表面的に話しているかいないかとは別にして、近藤先生のような質のもので(孤独を引き受けた上でのもので)、彼からして、僕が近藤先生に感じたような感じを僕に感じられていたら、もっと違った展開になっていたかもしれない、との考えも浮かびました。