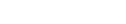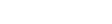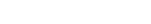親の呪縛から解放されて命を育てることは出来ますか?傷から傷を受け継ぐことになりませんか?子供を育てることとは?という質問をいただきました。
これは嬉しい質問です。書きたいことが沢山浮かんで来ます。、少し長くなるかもしれません。何回かに分けることになるかもしれません。
先日パンダの赤ちゃんの映像をテレビニュースで見ました。随分小さいのに驚きを感じました。親との体格差の物凄さに注意が惹かれました。出生時に、人間ほど親との体格差がある生き物はいないんじゃないかと漠然と思っていたのですが、そうではないことを知りました。でも、親との体格差が人間ほど長い時間続く生き物はいないのではないでしょうか?生命を維持するためにほぼ全面的に親に依存しなければならない時間を人間ほど長く必要とする生き物が他にいるでしょうか?
僕たちのほとんど全員が記憶していない時期のことを言っています。親と比べ圧倒的に小さい自分。全くあらがいようのない自分。そして、生き延びるために、親に見捨てられるわけにはいかない自分。記憶にないから想像するのも難しい感じがありますが、それでもあえて想像を逞しくすると、無意識のうちに、どうすればこの親に見捨てられずにすむのかと、必死の思いだったのではないでしょうか?
一方、実は僕には子供がいないのですが、子供がいたらどうだろうと、親になった場合の自分の気持ちを想像するのは難しくない気がします。子供への愛情が、本当に純粋で、無垢で、子供への思いやりに満ちたものであり得るだろうか?無私で無償の愛情を注ぎ続けることが出来るものだろうか?僕にはとても自信が持てません。これは僕が男だからでしょうか?男よりも母性に恵まれているだろう女性には可能なのでしょうか?女性にとっても、多分、不可能なことのような気がしてならないのです。
子供に向ける気持ちの中に、多かれ少なかれ、自己中心性が混ざることは避けられないのではないでしょうか?
そうした場合、そのことの子供への影響がどれほど大きいか、これまた想像でしかありませんが、圧倒的に無力な存在である子供にとって、とてつもなく大きいものなのではないでしょうか? 大人の目から見るとたとえ些細な自己中心性でも、子供にとっては全く違う大きさになるのではないか、この視点が大事だという気がして仕方がありません。
虐待というのは、一般的には、暴力とか、無視とか、そういうものを指して言われていると思います。大人の自己中心性のわかりやすいあらわれです。些細なものだとは言えないでしょう。このように、大人の側の自己中心性の程度の問題も勿論重要です。しかし、子供からすれば、大人の視点からは些細なものでも、とても些細なものだとは受け取れないような気がするのです。極論だとは思いますが、すべての子供は虐待を受けて育つ、そう言おうとしています。
子供の側からの有形無形の自発的な動きをどう感じどうレスポンスするか。親の側の自己中心性が、そのレスポンスの適切さを妨げ、子供の自発性との間でずれを生じさせる。そんなことが起きているに違いないと想像します。子供にとってはずれることがイコール虐待だ、そんな風に言いたいのです。
大人なら、相手とのずれを感じると、がっかりしたり、ショックを受けたり、傷ついたり、孤独を感じたり、腹が立ったり、感情の種類は様々でしょうが、とにかく、何らかの感情を感じることが出来ます。ところがどうも、その頃の子供は、僕の今までの臨床経験をベースにして想像するところでは、大人なら感じるだろうずれた時の感情を、感じないように、なかったことのようにするしかないようなのです。傷つくどころか、自分がいけないんだだめなんだとの罪責感や自己嫌悪がそこから生まれてくるようなのです。生き延びるためには親との一体感を維持するしかないと必死になってありとあらゆる無意識的な努力をしているように見えるのです。このことを親の呪縛と呼ぶのは無理がないことと思います。
すべての子供が親から虐待され、親の呪縛のもとに大人になっていく。そこに人間存在の悲しさがある。ここまでが、この質問に答えるための、前置きのようなものになります。