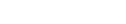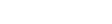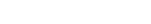孤立型については,自分のことを書けばいいから気が楽だ、手を付けやすい、という感じがありました。依存支配型の全体像について書こうとすると、筆が進む予想が立たず、書き出せないまま今に至ってしまいました。この辺で思い直し、現時点で書けることを書いて、そうしているうちに何か熟してくるものを待つという気持ちになって、とにかく取りかかってみます。
まず、依存型と支配型をまとめて依存支配型としてしまうこと、僕にはそのほうがしっくりする感じがあるのですが、その感じについて書くところから始めます。
典型的な支配型の人はなかなか我々の前に現れない、と言えそうな気がします。メンタルなことで他人の援助を求めるという行為自体が、支配型的な在り方と正面からぶつかりそうです。支配型的在り方で生きていくことに挫折を経験した人の多くは、解決のために別の方法を求めそうです。実際、こういう人を典型的な支配型っていうんだろうなあと感じた人は、僕の今までの経験の中でたった一人しかいません。その人の場合も、治療が長くは続きませんでした。支配傾向を指摘し、本人も自分にその傾向があるとちらっと口にするところまではいきましたが、その傾向に向きあって一緒に検討してみようというモードにはなれませんでした。
ということで、依存傾向が前景に出ている方々と多く接しているというのが僕の現実ではないかと思います。その現実をそのまま移して支配型をカットしてしまうことにしたかというと、それはちょっと違います。依存傾向が前景に出ている方々でも、程度の差はあれ、皆さん例外なく支配傾向を有していると僕には感じられます。他人を自分の思うように動かしたい。動かそうとする。ストレートに、命令する、要求する、指示する、という形を取らない場合でも、従属し依存する態度を取りながら、場合によってはその態度を利用して、相手を思うように操ろうとの意思が見え隠れしている。相手の期待に応え相手の期待を実現しながら、見返りを求める気持ちが働いている、何かを相手に期待している、あてにしている。
僕の記憶の中のたった一人の典型的な支配型の人。社会的に成功し、経済的に余裕がある。仕事を精力的、かつ完ぺきにこなし、部下に命令的、指示的に、厳しく接する。家庭内でも家族を自分に従わせる。車を何台も保有し、自分の歌をCDにし、自伝的な本を出版する。自己拡張的であり、直接的に他人を支配する。支配という観点から見たら、まことにわかりやすい。
前景に依存が出ていて支配が陰に隠れていたりストレートじゃなかったりという場合と、ストレートでわかりやすい支配。その関係をどう考えたらいいか。
前述の、典型的支配型の人と会っていた時の感触が記憶に残っています。話の中身と比べて、僕に対しての物腰は、他の、依存傾向が前景に出ている多くの方達と変わらないなあ、基本的に柔らかく、同調的だなあ、というものです。社会的な場や家庭内ではほとんどの人から怖がられ、本人も偉そうな態度を取っているに違いありません。その片鱗が面接場面で全く出ないではないのですが、しかしほとんどは頭が低い感じ。僕に配慮的に気を使う。こっちの感じのほうがこの人の元なんじゃないか、primary defenseはこっちだ、という気がしたものでした。
元は依存で、条件が整うと支配が前面に出る。そう考えていいのではないだろうか。
平の時に上司に胡麻をする傾向の強い人が、出世して上に立つと部下に対して支配的になる。運動部でしごきに唯々諾々と従っている人ほど先輩になると後輩をしごく。そんな現象を珍しくなく観察できるとしたら、依存と支配が結局は同じ事だ、元は依存だ、ということの証明にならないだろうか。
依存支配型の大きな特徴の一つに、上下関係への敏感性、というのを挙げたいと考えています。そのことについては項を改めて書く予定なのですが、ここでは依存と支配が結局は同じだという説明のためにこの観点を持ち出してみます。人間関係における上下関係へのアンテナが発達していて、自分を相手の下に置くか、あるいは上に置くか、常に立場を気にしている。前者が依存で後者が支配。前者がベースにあって、いつか自分が、依存しているその相手の立場になろうとする。すきを狙って後者の立場をうかがう。そのような心理が存在するような気がするのです。
依存と支配を一つにまとめ、依存するにせよ支配するにせよいずれにしてもあくまで人間関係の中で孤独感や不安の解決を求めようとする態度。その態度がメインである一群を依存支配型とする。それに対して、むしろ人間関係から離れることで安心を得ようとする一群を孤立型とする。このように人間全体を二群に分けてみる視点。三つや四つではなく、二つというところに意味があるような気がして仕方がない。
そして、一人の人間の中にも両方の傾向が存在している。割合に違いはあってもほぼ例外なく併存している。その人の本質を体感的に理解しようとする時、この人は根っこのところではどちらが優勢だろうかとの疑問が生じ、その答えを見つけようとする。答えが出ればその確証を得ようとする。僕が日々行っていることを、このように言ってもいい気がします。
依存と支配はそもそも別物ではないということに加え、依存と支配をまとめて依存支配型とし孤立型と対比させる視点が有益なものだと感じる。今回言いたかったポイントにやっと近づいた感じです。