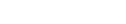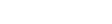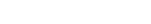『感じるって?』に続いて、もう少し"感じる"ということについて書いて欲しいとのリクエストがありました。
何かについて、「僕はこう感じる」と誰かが言い、別の人が「私はこう感じる」と言う。そういう会話が僕は好きです。何かは何でもいいんですが、例えば映画だということにしておきましょう。同じ映画を見た人が何人かで会話をしている状況です。「あの俳優が好きだ」「あの場面で感動した」「全体としてつまらなかった」「監督の意図がわかりにくかった」などと、ありとあらゆる感想があると思います。最初の、俳優についてだったら、「その人のどこが好きなの」との問いに、「ハンサムだから」と返事があり、「えっ私はちっともハンサムだと感じない。こっちの人のほうがずっとハンサムよ」というような会話がいい。その俳優について、映画評論家の誰かがこんなことを言っていたとか、その俳優は過去のどんな映画に出演していて奥さんはどこの誰だとか、そういう話も少しならいいんですが、ずっと続くとつまらない。それよりも、さっきのに続いて、「その人の他にも私はこんな人をハンサムだと感じる」「それは私の好みじゃない。大体私は顔にはあまり関心がない」「じゃあどこに魅力を感じるの」「演技力よ」とか、そんな風に続いていくのが素敵だと思います。この俳優のここが嫌いだいうお題のほうが、もっと盛り上がるかもしれません。いずれにしても、そう感じることが良いか悪いか、正しいか正しくないかから自由になって、それぞれの感じていることが主となって展開する会話が楽しい会話だと僕は思います。
私のクリニックでは、定期的にケースカンファランスをやっています。セラピスト達が何人か集まり、一人が自分の担当しているケースを紹介し、他の出席者がコメントを述べるというものです。治療経験のほとんどない、新しい出席者のコメントが、ベテランのそれよりずっと魅力的、刺激的だと感じることが時にあります。ベテランのコメントは、ステレオタイプ、ありきたりで、新人のは初々しくて力があるんです。まとまっているとか、間違ったことを言わないとか、そういう点ではベテランにかないません。断片的であっても、その人が本当に感じていることを言っている時、べテランのコメントよりずっとインパクトが強いのです。
私は、ケースカンファランスでは、自分が感じていることだけを話そうと心がけてきました。それをやっていると、孤独を感じます。自分が感じているのと同じように感じている人が自分以外にはいないと感じるからです。そんな時、自分の言ったことは間違っていたんじゃないか、見当はずれだったんじゃないか、という不安が生じます。「間違っていても、見当はずれでも、そう感じたんだから仕方がない」、理屈でそう言い聞かせても、不安はなかなか消えません。よくよく考えるとやっぱり間違えていた、浅はかだった、大事なところを見逃していた、ということが、まずはあります。そしてまた、自分の言ったことは、本当に自分が感じていることだっただろうか、感じていることを本当に正直に表現しただろうか、とも考えます。他の人の発言に影響されたり、間違いを恐れる気持ちが働いたりして、感じていることを歪めて言ってしまったと気が付かされることが少なくありません。本当に感じていることだけを表現するというのは、結構簡単ではないと痛感します。
そんなことを繰り返し経験してきたことと大いに関係していると思いますが、孤独を感じることに大事な意味があるのではないかという感じが、少しづつ強くなってきました。孤独を感じ、不安に耐えることが、さっきの、新人の初々しさに通じている気がします。そう言えば、近藤先生のケースカンファランスでのコメントは、初々しと言うと少し違うかもしれませんが、いつも生き生きとして力強かったことを思い出します。