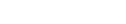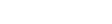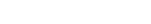ナルシシズムを実感し理解するとはどんな感じかを教ええてください。以下のことはポイントになるでしょうか?1、ナルシシズムと恥ずかしいという感情は関係しているか。2、ナルシシズムと健康的な自己肯定感の違い。3、相手を思いやるということ。 という質問をいただきました。
ナルシシズムの僕なりの定義から始めます。ナルシシズムを説明するために、まず、自意識を取り上げる必要があると考えます。自意識を、自分が他人にどう見られるかを気にする心理、と定義します。他人からどう見られるか、どう思われるか、自分が他人にはどう映るか、そこを気にする自意識心理のない人はいない。そう言っていいと思います。よく、「人目を気にしないで、自分のやりたいことを大事にしなさい」というアドバイスがあります。アドバイスとしてはいい場合が多いし、目指す方向としてなら賛成ですが、実現はほぼ不可能です。自意識がなくなることはまずありえないと僕には思えるからです。客観的には不可能ですが、そうアドバイスされた人の主観にとって、人目を意識している感じがなくなることは有り得ます。その時の心理状態をいわゆるナルシシズムと呼びたいのです。自意識が無意識になっていると考えていいと思うのです。これが可能になるのは、人からどう見られるかを気にする必要がないからです。それはつまり、見られる自分に疑いがない、自分に酔っている、難しく言うと、自己イメージに同一化している、ということ以外にはないと考えます。他人から受け入れられ賞賛されるに決まっているとの思い込みに成功している、とも言えるでしょう。
"いわゆ"ると書きましたが、"狭義の"ナルシシズムがこれだ、と言い直します。「世間に恥ずかしくないように頑張りなさい」との激励がよくあると思います。これは、狭義のナルシシズムを目指せと言っていることになります。狭義のナルシシズムを目指す気持ちがベースにあって、かつ自意識が無意識になっていない状態を、広義のナルシシズムと定義します。理想の自己イメージに同一化したいが出来ないでいる状態と言い直しても同じだと思います。
ご質問のポイント1には、答えたことになったんじゃないでしょうか?恥ずかしいという感情は、たいてい、僕の言う広義のナルシシズムです。恥ずかしいというのは、こうなりたいという理想イメージからのずれを感じた時に生ずる、と言えそうだからです。
健康的な自己肯定感とは、我々を超えた大きなものに生かされていると感じることだと思います。これ以外の自己肯定感には、程度の差はあれ、すべてナルシシスティックなものが含まれている、というのが僕の考えです。
相手を思いやる場合も、ナルシシズムが含まれていない場合はないと思います。医療関係、福祉関係に従事する人たちの利用者への思いやりにもそれを感じます。思いやっている自分にうっとりしている場合も決して珍しくないし、うっとりしていなくても、これでいいんだと思っていれば、それは僕の言う狭義のナルシシズムです。さらに広義のナルシシズムのない人、つまり、同僚、上司、利用者から、自分の思いやりの態度がどう評価されているかを気にしない人を、僕は想像出来ません。
僕のナルシシズム論を言い換えると、人間というものはそもそもナルシシスティックなものだ、そこから逃れられない、ただ、ナルシシズムを自覚する度合いを増やすことは可能だ、ということになります。
質問者に対しては、自意識を自意識として感じることを当面の目標としたらどうか、とのアドバイスが浮かびました。