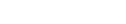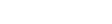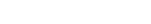このタイトルでブログを書こうと思うきっかけになった経験は、酒を飲むという行為に関するものです。
結論から先に言ってしまうと、酒を飲むという行為に強迫性が入っているのを発見したと同時に飲酒量が激減した、です。
昨年の暮れのクリニックの忘年会でこの話をしたら「年を取って飲めなくなっただけではないか」と茶化す人がいました。確かに老いと関係しているには違いないと思います。茶化した人の意図は、飲酒量の減少が強迫性の発見とは無関係に単に身体的な老化現象の表れではないかというもので、老いを否定的にとらえる気分が入っていると想像します。僕は新たに、この経験から、老いを肯定的にとらえる視点を提供してみたいとも考えています。
このブログの『生きているのが辛い』で、酒の醒め際に不整脈が出ることにきづいた、と書いています。そして、専門家に相談してその不整脈は気にしなくてもいいと言われたのに気になってしまう、止まるんじゃないかとの想像が走って心臓を見張ろうとしてしまう、と続け、それは自分の力で何とか生き延びようとする気持ちのあらわれではないか、委ねられなさと言ってもいい、無意識のうちに常に働いている心理ではないか、実は生きる辛さの元はここにあるのではないか、との仮説を述べています。その仮説は、自分の中で徐々に確信へと変化し、『不安 その五』では、自分の力で何とか生き延びようと必死になることが自己中心性の元だ、と書いています。そしてここで、強迫性の元もここにある、と付け加えようと思います。
早く行動しなければならないという僕のメインの強迫性が、母との付き合いにその根があるのは、『強迫性と自発性 その三』で述べたように、僕にとっては確信です。生き延びるために必要なものだったに違いありません。
さて、不整脈の話に戻ります。不整脈が原因となって心臓が止まるかもしれないとの不安に駆られ、心臓の動きを見張ってそれを何とか食い止めようとする心理(まさに強迫性)を発見したのと同時に、酒の醒め際に起きるんだから、不整脈を酒の飲み方への警告だと捉えようとの考えも浮かびました。意識的に酒量を減らそうと試み、まずは週2回を禁酒日にしました。
ここまで書いて、気づいたことがあります。これって、書くという行為にある強迫性を発見した経緯と似ているなあ、というものです。意識的に丁寧に書こうと試みたことがそれを妨げる強迫性に気づく契機になった。意識的に酒を減らそうと試みたことがそれを妨げる強迫性に気づく契機になった。そして強迫性に気づくと、丁寧に書くのが楽になる。酒を減らすのが楽になる。僕は今まで、強迫性に気付けば自然に自発性が増すと言い過ぎていたかもしれません。片手落ちだったかもしれない。強迫性に気づくためにも、意識してそこから抜け出す方向を模索するのが大事なのかもしれません。
さて、また酒の話に戻ります。週2回を禁酒日にすること自体はそれほど苦痛ではありませんでした。でも、飲んでもいい日になると、毎日飲んでいた時より酒量が増える傾向が出てきた。そして、やっぱり、翌朝、醒め際に不整脈が起きる。その頻度が増した感じもありました。そこで、どのぐらいの量を飲むと不整脈が起きやすくなるのか、酒量と不整脈の関係を観察研究してみようという気になりました。
そんな気持ちで過ごしていたある日、ある感覚がふと出てきました。表現すれば以下のような感じです。酒を飲もうとする衝動には何か無理がある。頭からのものだ、身体からのものじゃない。飲まなきゃいけないと思って飲んでいる。
この感覚の出現は僕には結構な驚きでした。酒が好きだから飲んでいる。酒自体の味もおいしいと感じるし、いい気分になって時間がゆっくり過ぎていく心地よさを味わえる。酒に強いから量がついついつい多くなるだけだ。酒の上で問題を起こすこともまずないし、自分の酒はいい酒だ。大体そんな風に思っていたのです。それが、好きには違いないが、それだけじゃないものが混ざっている。無理に頑張っているところがあるのは間違いない。飲むペースが速いのは、「早く行動しなければならない」につながっている。頑張る感じは歯磨きの時の力む感じに通じる。
そう感じたことと相前後して、ちょっと飲むとすぐ酔いを感じるようになりました。飲む時はビールから始めるのが習慣です。ビールはほんの前座、本格的に飲むための勢い付けのように位置付けていました。ビールなんて酒じゃないという感覚だった。それがビールを二口三口飲んだだけで、胸がドキドキして頭部がポーっとしてくる。あれっこんなに酒が弱かったんだっけ。これも驚きでした。今でも、そこを越して飲み続ければ、最初の酔いの感じがなくなって、結構な量を飲める。それも確かめてみました。でも、敢えてそうしようとは思わない。結果として、現在、350㏄のビール1缶と冷酒ぐい飲み1杯が定量。2年前までと比べるとまさに激減です。
若いうちは無理が効く。一つの行動に混ざっている強迫性の程度が強くても、その不自然さを体力が補ってくれる。不自然だと感じにくい。麻痺させやすい。歳をとるにつれて体力が衰えると、それが通用しにくくなる。それはしかし、不自然なものを不自然だと感じるチャンスを与えられたことでもある。強迫性に気付きやすくなり、結果としてより自然な方向への変化が起きやすくなる。自発性の占める割合が増すことになる。
これが老いを肯定的に捉える視点です。