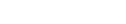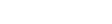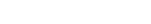薬物療法をどう考えますか、との質問がありました。
これまでこのブログの中で、私の考える治療を、人間としての成長を助けることだ、と言ってきました。人間として成長する。自己実現をを遂げる。感じる力を育てる。内部感覚(近藤先生の言葉です。そのうち詳しく触れることになると思います)を育てる。直観力を磨く。内省的になる。自己観察力が増す。パーソナリティーが変化する。これらの表現によって意味されるものは、みな似たものです。これらのことの延長線上に、悟る、救われる、大きなものによって生かされていると感じるといった宗教的な体験があるのではないか、というのが僕の考えです。もしその考えが正しいなら、そのプロセスを出来るだけ言葉にしていきたい、ひょっとしたらそれが自分の使命かもしれないとの気持ちがあります。実はこれがこのブログを書きだした本当の理由です。治療経験を通して、悟っていない自分が悟る方向に進んでいけたら、まさに現在進行形の自分の体験と重ねてそのプロセスを描写出来ることになるかもしれない、と考えたわけです。
薬物療法が、上記のプロセスに直接的に影響を与えることは、全くと言ってもいいぐらいないと感じます。
一方、以下に列記するようなものには、薬物療法が直接的に効果を発揮します。不安感。焦燥感。パニック発作。強迫観念や強迫行為。うつ状態。そう状態。幻覚妄想状態。イライラ感。激しい攻撃。興奮状態。などなど。
上記のような、いわゆる症状と呼ばれるものが良くなるのは、それらの底にある不安が薬物によって減少することによるのではないか、それが僕の印象です。本人には不安感が全く自覚されていないうつやそうも少なくありません。その場合も、潜在的不安が存在し、それが減少することによって気分の変化がもたらされると考えることが出来そうな気がします。不安の質や量の違いに対して、抗不安薬、抗鬱剤、メジャートランキライザーが使い分けられているだけだ、薬のターゲットは結局は不安だ、と言えそうな気がするのです。
私の考える治療が進展し、ある程度の信頼関係が出来、クライエントの安心感が増してくると、だからこそ不安を自覚できるようになる、ということがあります。ここで自覚されるようになる不安は、その後の治療の進行にとって非常に重要なものです。この不安にセラピストとクライエントが一緒に耐えていくのが治療だ、と言ってもいいぐらいです。
上記の症状の程度が激しいと、症状の底にある不安を自覚しそれに耐えるというのは困難です。薬物療法というのは、不安に働きかけ症状を軽減することで、もともとある不安を自覚しやすくまた耐えやすくするところに本来の意味があるのではないだろうか、それが僕の薬物療法観です。
少し現実的なことを書きます。薬物療法が必要な場合、精神療法に理解がある精神科医に薬物療法を受け、このクリニックでの治療と二本立てで治療を進めていくのが理想的なやり方だと思います。ご希望があれば信頼できる医師を紹介します。